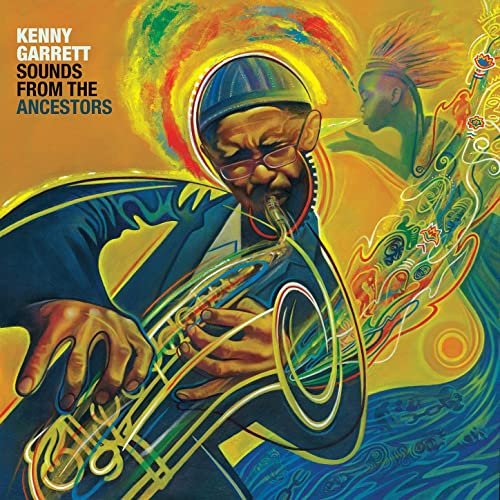「斯くあるべし」

ビル・チャーラップ・トリオの新譜である。
「大好きなんです!」という訳ではないが、
やはり聴かずにはおられない。
ブルーノート復帰作ということらしい。
まず、ジャケットが渋い。
一番左側が、ビルだが、ビルに見えない。
ウォールストリートの敏腕サラリーマンのようだ。
そして、これまで以上に選び抜かれた音使いであること。
どんどん余分なものを削ぎ落としていっている感じがする。
ビル・チャーラップ・イズムといおうか、イディオムというか、
少し音を間引いて弾き切らないビル特有のコロコロ奏法は、
いつも真似したいと思っているのだが、
いよいよ洗練されて、研ぎ澄まされた感じがする。
長年連れ添った、ピーター・ワシントンとケニー・ワシントンという
ビルイディオムを知り尽くしたサポートのなか、
必要な音だけ置いていく、紡いでいく、
「斯くあるべし」というように弾くビルの音楽の頑固さ。
美しさ。
構成、展開、ダイナミズム、グルーブ感、
どれをとっても非の打ち所がないピアノトリオアルバムである。
しかしあまりにも完璧で、面白味がないとも言える。
ピアノトリオの教科書のような演奏である。
でも、スタンダードを解釈する喜びも感じる。複雑な気持ち。
それにしても、相変わらず、ビル・チャーラは最高にピアノが上手い!
Bill Charlap(p)
Peter Washington(b)
Kenny Washington(ds)
1 The Duke (Dave Brubeck)
2 Day Dream (Billy Strayhorn, John Latouche, Edward Kennedy Ellington)
3 You're All the World to Me (Burton Lane, Alan Jay Lerner)
4 I'll Know (Frank Loesser)
5 Your Host (Kenny Burrell)
6 Out of Nowhere (Johnny Green, Edward Heyman)
7 What Are You Doing the Rest of Your Life?
(Michel Legrand, Marilyn Bergman, Alan Bergman)
8 Street of Dreams (Victor Young, Samuel M. Lewis)
やはり、冒頭の「The Duke」が白眉か。