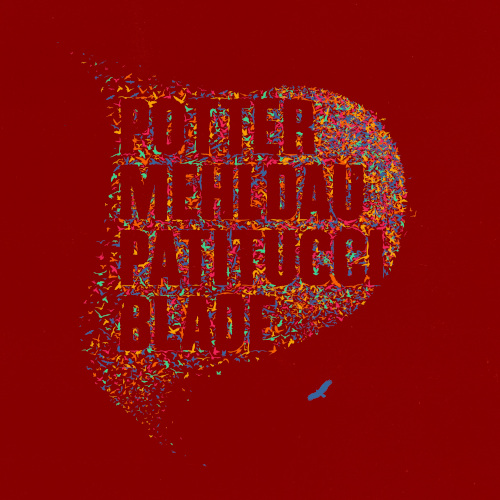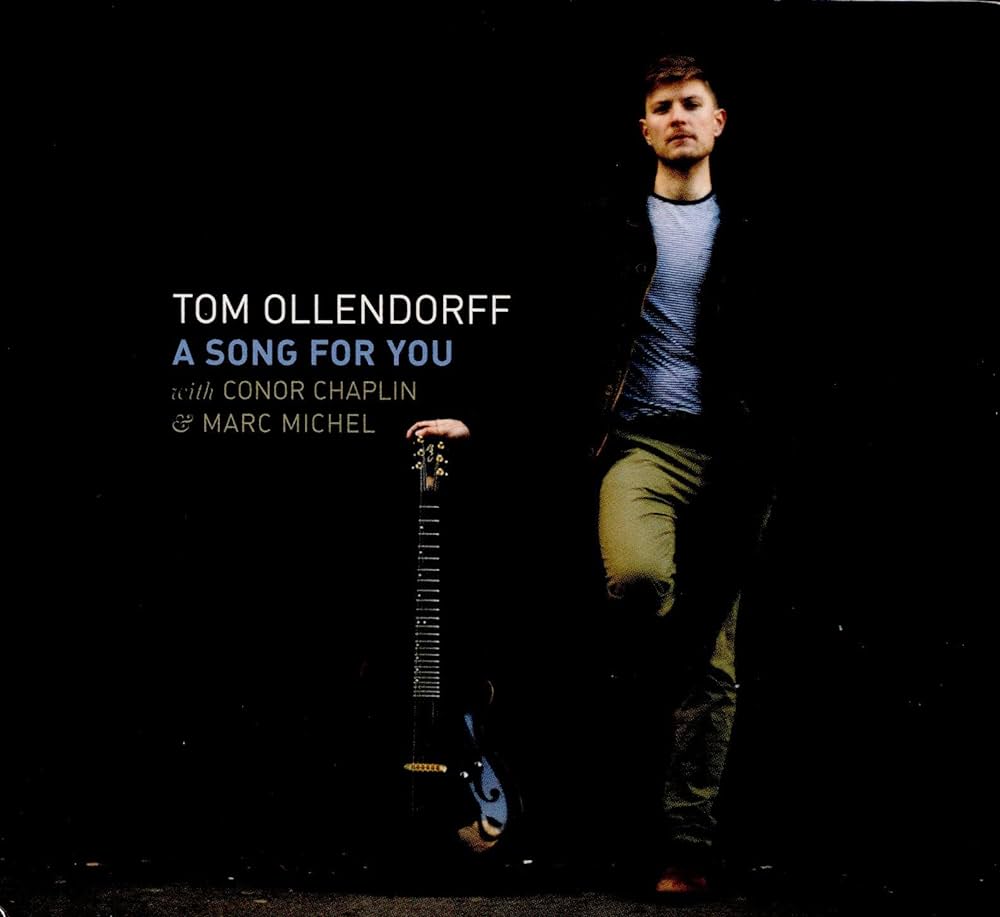ノックアウトしました。

なんといいますか、素晴らしいです。
最初の一曲目を聴いて、
「このまま、こんな感じで、最後までいってくれたらなあ」
と思いつつ、聴き進めていくと、
なんと、ちゃんと、私の心持ちに沿って、
静かに、揺蕩うように、優しく、
癒してくれた。
オーガスト・グリーンのアルバムでも聴いた
タイトル曲「Let Go」を聴くに至っては、
グラスパーのある本性の一部を垣間見たような気もした。
先入観というものは誰しにもあるものである。
もし、これが、グラスパーの作品と知らずに、
知らない新人アーティストの作品として紹介されたら、
ふうーん、で終わっていたかもしれない。
あのグラスパーが、こんな内省的な音像に徹した作品を
プロデュースしたことに感動しているだけなのかもしれない。
それにしてもだ、
いつまでもいつまでも浴びていたい音像である。
こういう音楽を創る心境になった
グラスパーの内因を知りたい気もするが、
どうでも良い気もする。
音楽へのアプローチの仕方として、
基調となるリフレインを繰り返す事を好むアーティストの
当然の帰結なのかもしれない。
あと、「アンビエント」なという
形容詞では片付けたくない、
もう少し新奇なディレクションを感じる。
ひとまず、
何かしら含みのある軽さと重さを備えた、
素敵なアルバムに仕上がっているとでも、
言っておこうか。
とにかく今の私の心象にピタリと嵌ってくるのが、
なんとも嬉しい限りである。
Robert Glasper(key),
Bernis Travis(b),
Kendrick Scott(ds),
Chris Scholar(g),
Meshell Ndegeocello(vo)
1 “Breathing Underwater” (feat. Meshell Ndegeocello)
2 “Your Eyes”
3 “Let Go”
4 “Inner Voice”
5 “Round ‘bout Sunlight”
6 “Going Home”
7 “That One Morning”
8 “Awakening Dawn”
9 “Luna’s Lullaby” (feat. Burniss Travis)
10 “Deep Down”
11 “Enoch’s Meditation”
12 “I Am”
13 “Truth Journey”