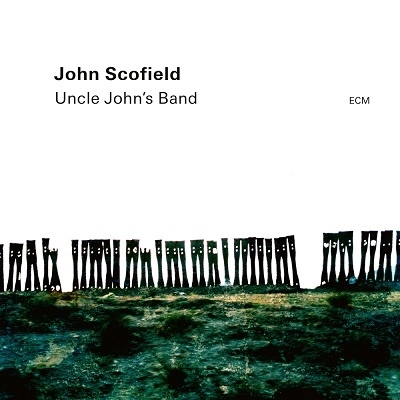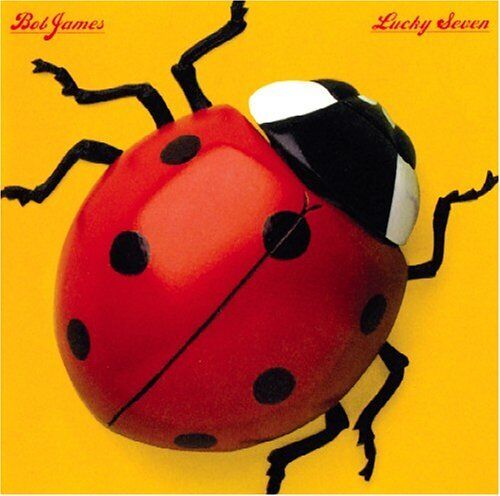ストーリーテラー
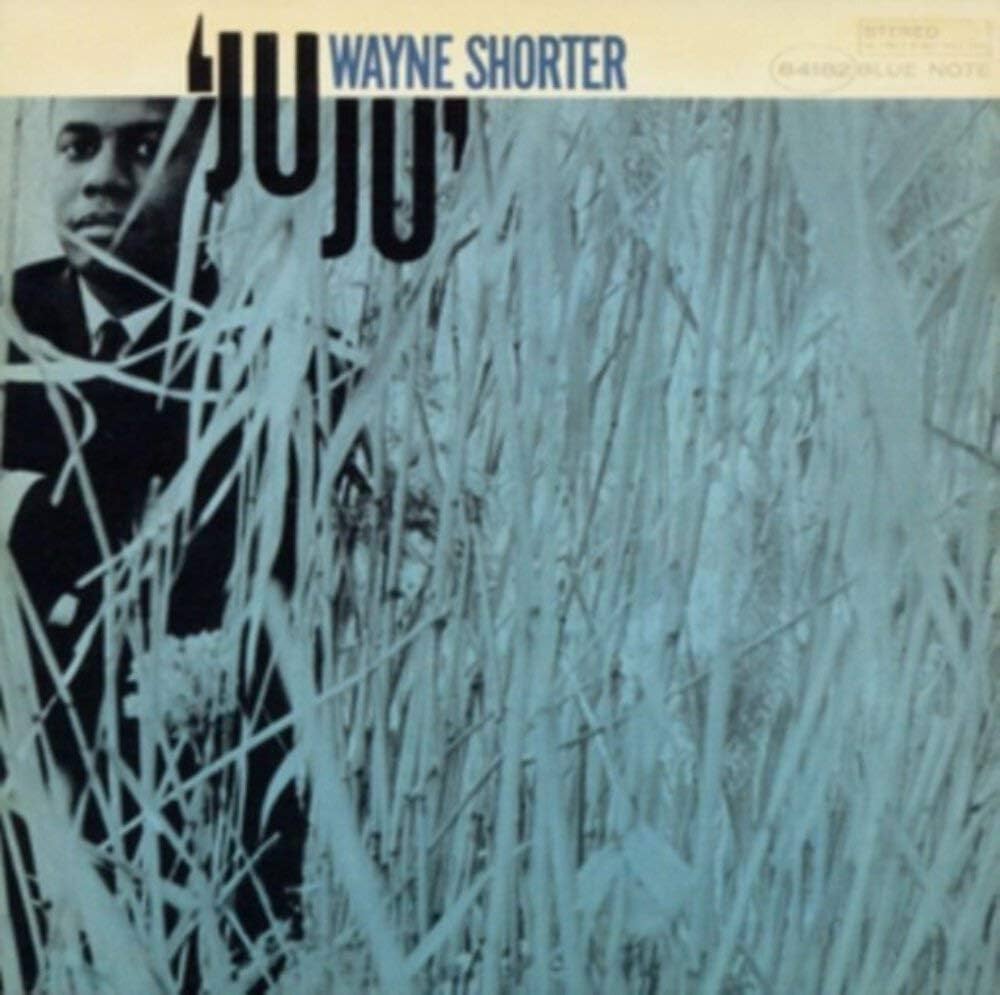
ショーターのドキュメンタリー映画「無重力の世界」を観た。
エピソード1~3と三部に分けて、ショーターの生い立ちから、
亡くなるまでの軌跡を丁寧に描いている。
面白かったのは、ショーターが音楽を志すことになった時のエピソード。
音楽のミューズが舞い降りた瞬間を語っている。
ショーターの演奏している動画(ウェザーリポート時代のものなど)を見ると、
この人はやっぱり、ちょっと変わってんなアと思う。
あまり表情豊かではないけれど、
時に、幼さやいたずらっぽさ、落ち着きのなさ、気まぐれさが、
仕草にストレートに表れている。
挙動不審な振る舞いながらも、演奏自体は、リズムは正確無比だし、
説得力の高い咆哮が空間を突き刺している。
多分、音楽を含め、世界の見え方(聞こえ方)が、常人と少し違っていて、
彼にしかできない独特の解釈、捉え方ができるのであろう。
ショーターの即興を聴くと、音空間の全容を瞬時に捉えたうえで、
余裕をもって、切り分け、色を添えていくといった展開力にいつも圧倒される。
その即興の素晴らしさは、なんといっても語り口のうまさ、ドラマ性にあるのだが、
もう少し分析的に、述べてみるならば、
フレーズの積み重ねや構成により、即興的にドラマ性が構築されているというより、
演奏する前から、語るべき「物語」が既に、厳然としてそこに存在していて、
ショーターのあの独特の音色と間合い(語り口)によって、
その物語が、色彩豊かに、この世に再現されるような感じを受ける。
即興であって、即興でないとでも言おうか。必然性の高い即興とも言える。
よく、アーティストの偉大さを表現する際に、
演奏する前から音が聞こえてくる(見えてくる)気がすると言われることがあるが、
まさしくショーターは確固たるストーリーテラーなのであろう。
そして、ショーターの語り口を、グループサウンドとして昇華したのが、
ザビヌル率いるウェザー・リポートであろう。
「ウェザー・リポートの真実」(山下邦彦著)を読めば分かるが、
即興の定着化(譜面化)というザビヌルが選択した手法は、
ショーターという稀有なクリエーターあってこその適した手法なのであろう。
このアルバムを久々に聴いて、興奮した。
ジョン・コルトレーンカルテットのリズムセクションを従え、
ワンホーンで繰り広げられるストレートアヘッドなショーターの咆哮に、
魅了されっぱなしである。
マッコイもエルビンも、親分のコルトレーンの時よりも
興奮している気がするのは、私だけであろうか。
全てショーターのオリジナルというのも珍しいし、
おどろおどろしさ、アジアンテイスト、コスモロジカル、黒魔術、モーダルさ、
などなど、
ショーターの謎めいた深遠な世界が概観でき、堪能できる傑作アルバムである。
1 JuJu
2 Deluge
3 House of Jade
4 Mahjong
5 Yes or No
6 Twelve More Bars to Go
Wayne Shorter(tenor saxophone)
McCoy Tyner (piano)
Reggie Workman (bass)
Elvin Jones (drums)
この冒頭曲のショーターのソロは本当にドラマティック。
私もソロのドラマ性を身につけたいが、これは天分か。