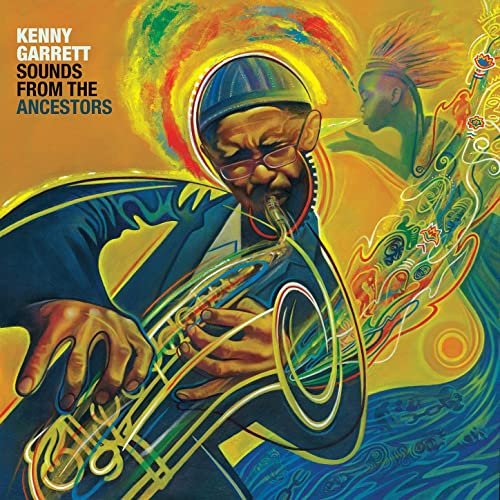Matt BrewerとJoe Lovanoの魅力

このアルバムは発売当時、
メンバーの人選、構成力、選曲のセンス、
どれをとっても、聴く前から興奮していたのを、思い出す。
フロントの個性をいかに、引き出すかということにポイントをおいて、
聴いてみると、これまで気づかなかった、リズムサポートの妙のようなものに
改めて気づかされる面白さがあった。
このアルバムには、アントニオ・サンチェスの嗜好や方向性、こだわりが、
ストレートに表現されていて、その意気込みを感じるのは当たり前なのだが、
フロントのサポートとして、ベースを誰にするかという人選において、
サンチェスの慧眼に敬服するのである。
メルドーには、マット・ブリューワー
ジョンスコには、クリスチャン・マクブライド
ジョー・ロバーノには、ジョン・パティトゥッチ
合わせる前からでもなんとなく、想像できたかもしれないけれど、
実は、一緒に演ってみないことには、分からない未知の領分が、
サンチェスにとっても、ワクワクする人選であったと思う。
組み合わせの妙。一つひとつが魅力ある素材の編集工学。
中でも、今回聴き返してみて、新たな発見であったのは、
・マット・ブリューワーのベースの魅力
・ジョー・ロバーノとジョン・パティトゥッチとの相性の良さ
の2点である。
まず、マット・ブリューワー。
メルドーといえば、ラリー・グレナディアがまず思い起こされるが、
マットの何か、無骨で太く、奥まったような定位のベースが、
メルドーの茫洋で捉え所のないメロディをガチッと掴み込んでいるような感覚は、
ラリー・グレナディアの時のドライブ感とは異なるものを生み出している。
簡単にいうと、非常に「より嵌っている」という感覚、気持ちの良さである。
ぜひ、このトリオでの、作品のリリースを願うばかりである。
次に、ジョー・ロバーノ。
ジョン・パティトゥッチのリーダー作「Remembrance」(2009年)でも
トリオ形式での、ロバーノとの相性の良さは、経験済みであったが、
その時のドラムは、ブライアン・ブレイド。
今回のこのトリオにおけるジョン・パティトゥッチは、
実にはじけていて、ドライブ感のあるベースで、ロバーノを煽っている。
相性ぴったり。素晴らしい。
「ジョー・ロヴァーノはあなたにとってどんな存在なのでしょう」
というサンチェスに対してのインタビュー記事で、
「ジョーとは数回しか共演したことがなかったけど、彼の音やアプローチに心酔してきた。ずっと好きだったんだ。よりオープンで自発的な音楽をこのトリオに求めていたから…本当に素晴らしい結果だね」
と答えている。
うんうんとうなづきながら、至高の三者三様の饗宴に酔いしれる一夜でありました。
■CD1
Brad Mehldau(p), Matt Brewer(b), Antonio Sanchez(ds),
Recorded in New York on 27 October 2013
1. Nar-this (Nardis - Miles Davis)
2. Constellations (A. Sanchez)
3. Big Dream (A. Sanchez)
■CD 2
T-1 - 3
John Scofield(g), Christian McBride(b), Antonio Sanchez(ds)
Recorded in New York on 4 December 2013
1. Fall (Wayne Shorter)
2. Nooks And Crannies (A. Sanchez)
3. Rooney And Vinski (A. Sanchez)
T-4 - 6
Joe Lovano(ts), John Patitucci(b), Antonio Sanchez(ds)
Recorded in New York on 16 December 2013
4. Leviathan (A. Sanchez)
5. Firenze (A. Sanchez)
6. I Mean You (Thelonious Monk)
メンバーは、サンチェスとマット・ブリューワー以外は異なるが、
冒頭曲Nar-this(ナーディス)の再演。
カクンカクンとキレの良い、マットのベース!